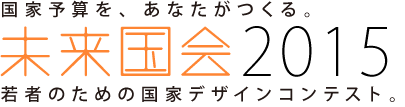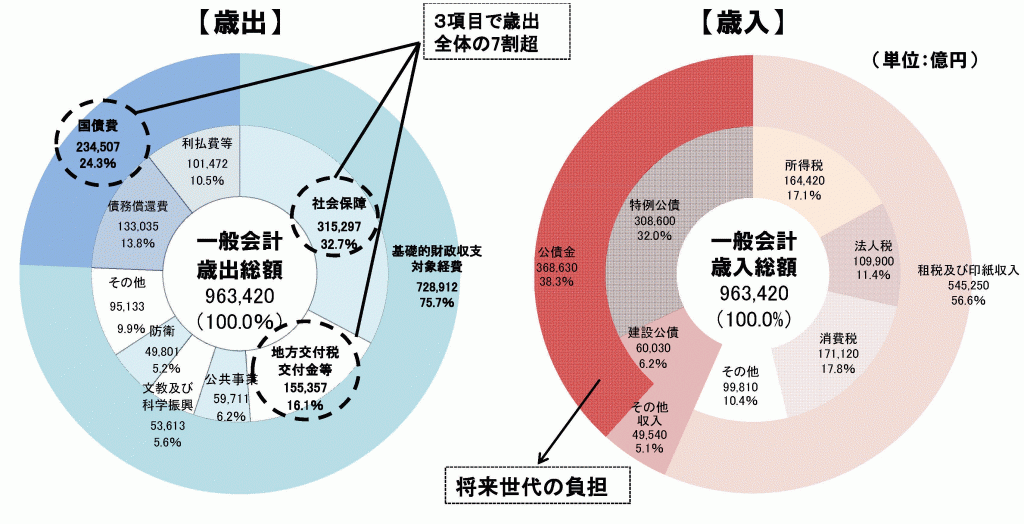みなさんお久しぶりです。
未来国会運営チームの山本です。
いよいよプログラムも終盤です。
予算案を課題として提出してくださった方々のフィードバック等を行っている過程で、もう少し深く考えたほうがいいと思う点がありましたので、今回はそれについて書きます。
予算を一度組んでみた後、本当に自分たちの予算が正しいのかということを判断する材料として用いていただきたいです。歳出歳入の各項目について述べますので、自分たちが変更した項目について参照してもらうだけでも、意味があるのではないかと思っています。
今回のコラムの概要を説明すると、こちらは2つのコラムで構成されています。
前半:平成27年度予算の確認 〜 歳出のキーポイント
後半:歳出のキーポイント 〜 まとめ
なんども言いますが、必要なところだけ敲きとして読んでもらえれば幸いです。
〜平成27年度予算〜
ところで、皆さんは内閣府や財務省が発表している平成27年度予算案をご覧になったことがありますか?
平成27年度予算は以下のようになっています。
出典:財務省『平成27年度一般会計予算(平成27年4月9日成立)の概要』
[URL] https://goo.gl/1u5bw1
予算の規模は96兆円となり、依然として莫大な額の予算を計上しています。グラフ上でも指摘されている通り、社会保障、地方交付税、国債費で歳出は全体の7割を超えています。歳入の部では、36兆円もの公債金が発生し、将来世代への負担が増加していることも見て取れます。公債金の中でも特例公債は30兆円を超えていて、特例公債だけで、歳出の国債費を上回っているという現状も注視しておく必要があるでしょう。
以下では、歳出、歳入の順番で各項目について私からみなさまにお伝えしたいことについて書かせていただきます。
〜歳出編〜
まず歳出について見ます。
このグラフを見る限り、将来も問題になるだろうと思われるのは、「社会保障」「地方交付税交付金等」「国債費」の三つです。もっと細かく見れば、防衛費や文教及び科学振興費をどうするかという問題はあります。ですが、今回は上記の三つについてひとつひとつ見ていくことにします。
・社会保障関係費
社会保障というと何を考えるでしょうか?
上記の坂田先生のサイトでは、社会保障関係費は生活保護費、社会福祉費、社会保険費、保険衛生対策費及び失業対策費の5種類に分類されると書かれています。言われてみれば確かにそうだなあと感じるものばかりではないでしょうか?
社会保障の中にはもちろん、年金や医療費も含まれます。現行の制度だと、年金の給付は高齢者のほうが多く、医療費の負担は高齢者のほうが小さいです。つまり高齢者が増えれば、年金の給付額が増え、それと同時に一人あたりで国が負担する医療費も増えることになります。年金や医療費が増加すると当然、社会保障関係費も増加することになります。
ここで起こる議論が、「そんな社会保障にお金を割くくらいだったら、自分たちのしたいことに税金を割いたほうがよくないか?」という議論です。その問題意識はとても良いと思います。
ただし考えなくてはならない点が一つあります。それは、社会保障関係費のどこを削ることができるのかということです。単に削る削るというだけでは説明力がありません。では、どこをどのように削減していくのかという説明が必要になるのです。
また、そのとき考えなくてはならないこととして、「社会保障の中の◯◯を削ったら、これくらいの余剰が出ます。」というときの金額をある程度、測ってみてください。例えば、高齢者なら、今これくらい高齢者がいて、年間何人の人が病院にいくのか。そのとき国が負担している額はこれくらいであるから、それをこのくらい削減できる。なぜなら〜という形で考えて行って欲しいです。
安易な予測だけはやめてください。
そこ削ってそんなに余剰出ますかという問いをされるくらいなら、しっかりと考えておいたほうが合理的ではありませんか? 社会保障は金額が大きい分、政策次第で削ることはいくらでもできるでしょう。だからこそ、適当に考えるのではなく、自分たちや他の人の生活を維持するための費用なので、しっかりと考えて予測をしてもらいたいです。
・地方交付税交付金
地方自治法第1条の2では、「地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」と規定され、「住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねる」としている。国には、そのサポートをする役割があるのです。少し難しい法律の話から始まりましたが、地方交付税について少し見てみたいと思います。
詳しい税金の内容は
がとても参考になります。
地方交付税を削減しようとする時、少しだけ思い出してほしいことがあります。小泉政権の時、三位一体の改革として地方交付税交付金の見直しが行われました。これによってある程度、地方分権が進んだと言われたりもします。
では、この時交付金の見直しを行うと同時に、小泉さんは何をしたのでしょうか? それは、地方への税源移譲でした。国税を減らして地方税を増やしたのです。つまり、交付金を見直す代わりに、自分たちで操作することができる税金を増やすことで地方分権を進めたということになります。
このことを踏まえて、予算を考えていくと、単に地方交付税を減らすということだけをするのは避けるべきであると考えられます。実際、地方交付税を交付してもらっている地方自治体は全国にたくさんあります。何も代替案なく削減をすれば、地方自治法の「身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねる」という原則に反してしまうことになります。
うまく国家予算を減らしつつ、地方の行政を維持させるような施策を考えないと、安易に交付税交付金を減らすという決断はできないということでしょう。
そのあたり難しいかもしれないですが、考えてみる価値はあるかもしれないです。
・国債費
国債費について考える際に、
大事な点として、『ライフサイクル仮説』という仮説があります。
AllAbout ビジネス・学習
『早わかり消費(3)「ライフサイクル仮説」とは?』
厳密には、いろいろな条件が付くのですが、ごくごく簡単に「ライフサイクル仮説」を説明すると、
若者は将来のために貯蓄をして、高齢になるとその貯蓄を崩して消費をする
というものです。
よく考えてみれば、案外間違ったことは言っていないような気がしませんか?
大学生には実感がないかもしれないですが、周りの先輩とか見ていると「◯◯するために貯蓄してます!」という人がいたりしますよね。将来、結婚したい人、こどもが欲しいと思っている人は特にそうかもしれません。そして、定年を迎えて仕事を引退したら、そこまで貯蓄したお金を使って、旅行に行ったり娯楽を楽しんだりしてますよね。よく電車に乗ると、そういう人たちをターゲットにした旅行プランの宣伝があったりしますよね。この仮説に基づいて考えるとあながち間違っていないのかなという印象を持ちますね。
このことを踏まえ、高齢者が増えている現状を考えると、将来的には日本国内の貯蓄額は下がっていくのではないかと考えることができます。これはどういう問題を生むのでしょうか。
みなさんは日本の債務総額をご存知ですか?
リアルタイムで確認したいなら、借金時計をみるといいです。
これをみると、日本の債務総額が約1020兆円(だいたい1000兆円とおぼえてもいいと思います)ほどあるということがわかります。一人あたりの負担額も記載されているので確認してみてください。
みなさんは、「日本がデフォルトにならないのは、国の中で国債を消化できているからだ」という類の話を聞いたことがあると思います。その話には大きく日本の預金総額が関係しています。日本の預金総額は1500兆円と言われてきました。最近の記事では1700兆円になったというものもありました。純資産(海外の国債なども含めたもの)は2000兆円ともいわれています。
Garbage NEWS.com
『日本の家計資産残高は増加、1708兆円に…日米家計資産推移(2015年Q1分)(最新)』
自国の通貨で管理できているからデフォルトが起こらないという話を聞きますよね。先ほど見たように債務総額が1000兆円、預金総額が1500兆円であるとすると、一番上の平成27年予算を見たとき、公債金ー国債費はだいたい10〜15兆円であると考えることができます。さらに、ライフサイクル仮説が正しいと仮定すると、預金総額は高齢化とともに少しずつ減少していくと考えることができます。そう考えるといずれ預金総額を債務総額が上回ると考えることができます。(インターネット上では様々な意見があるので、明確に何年とまではここでは述べません)預金総額=債務総額、さらに預金総額<債務総額となる日が将来くるのであれば、今まで通り国債を発行し続けていいのかという疑問が生じませんか?デフォルトするにしろしないにしろ、このまま借金を増やし続けるのは、世代間の公平性にかけるとは言えないでしょうか?その点も踏まえて予算を作ってみて欲しいです。
ただ、ライフサイクル仮説が一概に正しいかというと、そうではない点もあります。日本では、高齢者の貯蓄率も高いという論者もいます。よく考えれば、死ぬ時に財産がゼロというのはなかなか起こり得ない事象で、現実的には高齢者でも貯蓄をして生活していくというのは、納得できる見方であると考えられます。もし、そのように考えるのであれば、ちゃんと自分たちの意見を論理的に整理して、予算案を作成して欲しいです。
続く後編では予算の歳入についてみます。
どのように税金をかけていくと良いのかということを見ていきましょう。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
未来国会運営チーム
山本隼汰